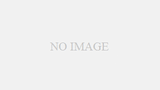※当記事は一部畑恵 ブログから引用しております。
日本では1990年代のバブル崩壊以後は、失われた20年と呼ばれるほどに長くデフレが続いています。
そこで、今から3年半前には自民党に政権が移り、デフレ脱却に向けた政策を強力に推し進めることになります。
政府ではデフレの脱却のために金融政策および財政政策、成長戦略の3本の矢を掲げたアベノミクスをスタートさせています。

アベノミクスの最初の段階では、3本の矢の中の金融政策が最も大きな効果を発揮しています。
日銀では政府と協調をして本格的な金融緩和を実施しています。
本格的な金融緩和政策が実施されるごとに為替市場では円安が進行することになり、輸出企業を中心にして企業業績が上昇することが起こっています。
その結果として、大企業などでは賃金のベースアップが行われて、日本の景気が一時回復傾向となっています。
また、外食業界などでは人材不足が起こるほどに失業率が低下して、就労環境が改善する状況が生まれています。
しかし、景気が回復する中で行った消費税の増税が予想以上に景気の足を引っ張る結果を及ぼしています。
そのため、消費税が5%から8%に上がった後は、国内の消費が停滞することが起こっています。
消費税の増税によって人々の消費マインドが、再び節約志向に向かいそうな兆しが出てきます。
2016年8月には大規模な財政支出を行うことを決定して、アベノミクスをもう一度軌道に乗せようとしています。
リニアの整備を従来よりも短縮したり、1億総活躍社会に向けた予算を配分することが予定されています。
アベノミクスは4年目に入り、金融政策はマイナス金利まで踏み込むなど限界が見え始めています。
そのため、財政政策を強力に推し進めることで、デフレからの脱却を確かなものにする試みが行われることになります。
去年には消費税の再延期が決まり、今年には大規模な財政出動をすることが決まっています。
今後は財政出動の効果のいかんによって、アベノミクスが継続できるかの正念場を向かえることになります。
最終更新日:2016年9月1日